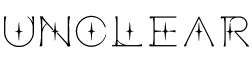
→前のページへ戻る
サンプル
冒頭:1〜3p
01:2月4日(水)
白く冴え冴えとした月が、ぽかりと空に浮かんでいた。見上げた明るさとは対照的に地上はいっそう黒々として見える。闇の中に木々の輪郭がぼかされている。辺りを歩く人の姿はなく、家の窓から漏れる光も遠い。
その人影は、佇んでいた窓辺で息を吐いた。外の気温は落ち込んでいるはずだが、室内にいてはそれも感じ取れない。窓ガラスは白く曇ったもののすぐに元の透明に戻った。影は部屋から外を覗いて、自分ひとりだけが起きているようだ、と妙な感慨を覚えた。
踵を返して窓から離れる。リノリウムの床に、キュ、と靴裏が擦れて音を立てた。白く均一に塗り込められた四角い部屋に、唯一置かれた家具であるベッドに近づく。布団を持ち上げて中に入るということはせず、隅の方に浅く腰かけた。
「…………、」
唇を薄く開いたまま沈黙する。目だけが忙しなく、同時に冷静さを伴ってベッドの周囲を走る。シーツも掛け布団も、全てが白い。
ベッドの中には先客がいた。いや、正しく言うならば、そのベッドは購入されてこの部屋に持ち込まれた時からずっと、同じ人物によって使われ続けているのだった。
ベッドの中に行儀良く収まっているのは、十六、七くらいの見目をした少女である。布団はきちんと上まで引き上げられて、そこから両腕が真っ直ぐに延びていた。背中の半ばまで伸ばされた黒髪は乱れもなく、身を包むパジャマには皺がない。少女は穏やかな表情で、身動ぎもせずに眠っていた。呼吸による胸の上下さえ見て取れない。
人形のようだ、と影はいつも思う。その薄い瞼は二度と上げられることがなさそうで、裏で夢を見ているとは到底思えない。
思えないけれど、少女は生きている。生命活動は未だ続けられている。ピ、ピ、ピ、ピ──と。規則的に響く無機質な音が、もうずっと前からそれを主張し続けている。ただ、傍らにある、透明な液体で満ちたイルリガートルと、そこから伸びるチューブが見る者の瞳に冷たく映る。
今日の日付を思い返した。二月四日。そして、少女の誕生日は二月六日。その日をもって少女は十六歳になる。誕生日には、少女の両親が涙ぐみながらこの部屋にやって来るだろう。その手には大きなプレゼントを抱えているはずだ。誕生日の感激で少女が目を覚ますことを祈って。
影は上半身を屈めた。少女の髪の一房を手に取り、そっと口元へ寄せる。髪へ口づけるかのようなぎりぎりの位置を保ったまま、影は囁いた。
「誕生日おめでとう、を当日に言えなくてごめん。しかも、プレゼントをあげるどころか、あなたの物を勝手に持って行くことになる──」
言うや否や立ち上がり、壁のフックに下げられていたハンガーを手に取る。それに通された濃紺のセーラー服を腕に抱えると、抜き取ったハンガーだけを壁へ戻した。
「これ以上《代わり》は出来ないし、それにもう厭なんだ。……ごめんね」
再度、謝罪の言葉を口にする。
まだ一度も袖を通されていないセーラー服を持って、影はするりと、音もなく部屋を出た。
全てを照らす月はたださやけく、沈黙を保っている。少し風が出てきたのか、朧げな雲がたなびいていた。
抜粋:17p
押し出した呼気が途端に白く染まるのを見て、ああ、冬だな、と、今さらながらにそんな感想を抱いた。体内と外気の温度差で真っ白になった息は、風に乗って流れていく。
井々城千草(いいしろ・ちぐさ)は歩道橋の上で欄干にもたれかかり、過ぎ去っていく車を見るともなしに見ていた。待ち合わせなど、ここにいなければならない事情がある訳ではない。下校時に単なる気まぐれを起こしただけのことだ。千草は雑踏に消えゆく人の後ろ姿や、目くるめく勢いで走り去る車を俯瞰するのがそこそこ好きだった。
手すりに手のひらをつけたまま腕を伸ばす。それによって肩からずり落ちたリュックサックを元の位置に戻した。
千草は黒いダッフルコートを着込み、カジュアルなデザインのリュックサックを背負っていた。コートの下は同じく黒色の学生服である。詰襟の、いわゆる学ランというものだ。襟の校章はここからJRで三十分ほど揺られたところにある共学制高校を示していた。千草はそこの二年生だった。と言っても、あと一ヶ月ほどで二年次を修了し、三年生に進級する。
「…………、」
再び唇の隙間から息を零し、ふとコートのポケットからスマートフォンを取り出す。本体を金属ケースで包んでいるために指先へひやりとした感覚が忍び寄る。最早慣れたことなのでさほど気にせず、画面を点灯させた。それは現在時刻を確認するための行為だったのだが、メールが一件届いているのに気がつく。
…
抜粋:120p
店員を呼んで千尋の選んだパンケーキ二つを注文する。待つこと二十分ほど、届けられたニ皿は非常にきらきらとしていた。焼きたてのやわらかな香りが鼻腔に届く。ひとまず一皿ずつ自分の前へ持っていく。黄金色に焼けた分厚いパンケーキの中央に君臨しているのは高さのあるホイップクリーム。その周りを苺、ブルーべリー、フランボワーズ、といった赤や紺の果物が取り囲んでいる。その傍らに小さな器が添えられていた。中には艶めいたメープルシロップが入っている。続いてもう一皿はクリームチーズが乗ったもの。その上に蜂蜜がきらきらとした斜線を描いている。さらに細かく刻んだクルミが散りばめられていた。千尋は二種類のパンケーキを前にして、喜びを隠し切れない様子だった。
「いただきます!」
「どうぞ。俺もいただきます」
千尋は慣れない様子でナイフを動かし、口へ入れる。
「……っ」
至福の極みだという笑顔だった。作り手に見せれば、さぞや喜んでくれるだろうと思われた。千草は思わず、自身の口元に手を遣る。同じ顔なのにああも口角が上がるらしい。
…
→前のページへ戻る